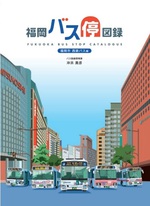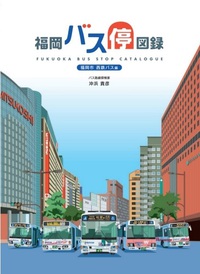2009年12月05日
大蔵(おおくら)


北九州市の「大蔵」。ここは「おおくら」です。
旧電車通りと大蔵川や「44」のバス路線が交差していて、
地形的にも複雑なところです。



「44」東大谷方面は、は大蔵の交差点から大蔵中学校のある高台へ分岐するので、
バス停は電車通りと並行する坂道の途中に設置されていて、立体的な構造になっています。
ちなみに本道が走っているほうは、あまり「山」という感覚はないのですが、
全体的に台地地形で、山陽新幹線のトンネルはこのほぼ真下を走っています。


反対側、八幡中心部へのバス停付近は道路の拡張工事がおこなわれていて、、、
と、まあいかにもリアルタイムのレポートのような書き方をしておりますが、
この写真を撮ったのは9月の27日ですので、
現状すでに道路の風景などはかなり変わっていることが予想されます。すいません。



工事が行われている山側に公園が設置されており、
ここが鹿児島本線の旧山線「大蔵駅」があったところと推測されています。
駅の位置はこのへんでほぼ間違いはないんですけれども、
なにぶん昔のことですので、路線配置やら駅舎については資料がすくなく、
推測でしか語れない部分も多いそうです。

そんな昔のことにもかかわらず、大蔵川には鉄道が渡河していた名残の煉瓦積み橋台が。


行政が立てた看板の表記は「板櫃川」。
それに対して「大蔵川と金山川が合流した先が板櫃川で、ここは大蔵川だ」と主張する、
地域住民が立てたと思われる看板もあります。わたしにとってはどっちでもいいですけど。
自宅のすぐそばを流れる川を、私は小さい時の名残で「いなつかがわ」と呼びますが、
油山川(あぶらやまがわ)って名前が正式名称のようで、
21世紀になってから生まれた息子たちは、「いなつかがわってどこ?」って反応します。
でも「ここは稲塚川だ!」と主張する気もないですし。
いまの飯倉4丁目あたりは、むかし大字稲塚でした。
「稲」が集められる「塚」すなわち食糧である「飯」の「倉」なので、
どちらも同じことを示す地名なんですけど、けっこう印象が違う気がします。



そんな大蔵川は豊前と筑前の境界となる川で、ここに架かる橋なので、「両国橋」です。
架け替えられる前の橋の一部が、現在の橋のそばに保存されています。



橋の北側も道路拡幅工事の真っ最中です。

本道の大蔵バス停や大蔵交差点からはけっこう離れているんですが、



こちら大蔵二丁目交差点から南に折れたところのバス停も「大蔵」です。


そして、こちらの大蔵バス停のすぐ南の道路反対側にもバス停が立っていますが、
こちらは「神田橋」です。南行きの神田橋バス停は南側交差点よりさらに先にあります。
バス停板の表記に遺っているように、もともとは到津から小倉方面に路線があったため、
小倉から来たバスが停まるための大蔵が、↑のバス停です。
この「56」の砂津行きと八幡駅行き、
福岡の「3」で言えば天神行きと藤崎行きみたいなもんだと思うんです。
市のいちばんの中心地までいくものと、区役所のあるそこそこの繁華街にいくもの。
でも天神行きのほうが先に廃止されることは福岡では考えづらいので、
北九州は市域の広さや各区の独立性の高さ(あくまで福岡と比べて)なんかが感じられて、
地理学的な人間の行動パターンの研究材料としても面白いと思います。

現在は上重田や田代に行くバスは、八幡方面からこのように右折してくるものしかありません。
そのため、本道上とココと、「大蔵」バス停に2度停車しています。
完全な免許維持路線のようです。
これを免許維持路線として残しているということは、
やはり交差点の右左折も要認可ってことでしょうか。
56番(あと54番も)の砂津行きは最終日に乗りに行った記憶があります。乗客はまったくの皆無で、バスファンのかたがたもあまり乗らずさびしく廃止になっていくものだなぁ、と思ってしまいました。
大蔵の道路拡張工事についてですが、ちょんびんさんが撮った写真の状態からまったく変わってません(笑)しかし、今の状態だとバス停に停まれるのが一台だけという状況ですので早く拡張工事が終わることを願ってたりしています。
大蔵線の橋梁跡が残っていることにはまったく気づきませんでした・・・。昔が偲ばれるひとつのすばらしい遺産ですね。
初めてで長文となりましたが失礼しますm(_ _)m
本日のテーマではなく申し訳ないのですが、「稲塚」から「飯倉」のお話、大変ためになりおもしろかったです。地名はいろいろな歴史をたどっているんですね。
今日のちょんびんさんの記事は「ほぉ〜!」「へぇ〜!」が非常に多く、あまりの面白さに「明日、誰かに話したくな」りました。
大蔵、変わってませんか。
民主党政権になったのも影響しているかもしれませんね。
今年はホリデーアクトパスの関係で、
なるべく費用がかさむところから優先していました。そのため、
来年パス販売がなくても一日乗車券でまわれる北九州が、
いちばん疎かになっております。
でも継続販売も決まったようですので、
来年は北九州を中心に据えてみたいと考えています。
どうぞ地元の方の情報、これからもよろしくお願いします。
今年3月に香椎~古賀が廃止になった際、
最後のバスに乗りましたが、ファン乗客は9名ほどで、
私も「あれ、路線廃止を惜しむ人々って、こんなもん?」
と残念に思っていました。
城南線経由の「18」最終は誰一人としていませんでしたし、
「56」も砂津までの路線上にバスが走らなくなるわけではないので、
そこが重要視されなかった理由かもしれませんね。
6月の中央ふ頭→千鳥橋や野芥二丁目には、
バスの席が埋まるくらいのファンが集まっていました。
いつもは誰も乗らないバスが、廃止の時だけ騒々しくなるのは、
人によっては苦々しく感じられるものかもしれません。
けれども、そこにバス路線があった記憶を共有する人は、
多くいればいるほど嬉しいことだと感じています。
ということで、若い世代の積極的な活動を応援します。
私も、西鉄一般路線バスが赤白色でなかった時代を知る
最後の世代として、ほどほどに頑張ります。
>今日の記事は「ほぉ〜!」「へぇ〜!」が非常に多く
どこにそう感じていただいたかはわかりませんが、嬉しいです。
西鉄バス路線の変遷を追うことが、
そのまま福岡の近現代史を追うことに
つながればいいなぁと思うことがあります。
路線の改変は人の動きの変化に伴うものですから、
それは住宅地の開発であったり、産業の勃興であったり、
あるときは衰退であったりします。
それからバス停の名前って、
現在の行政区分上では消えてしまった小字や旧町名を、
比較的よく残していると思います。
苗字もそうなんですが、すでに使われているものは記号化してしまい、
例えば「両国」といわれても、なぜそこが両国なのか、
あえて意識することは現代ではすくないですよね。
でもこの「大蔵」に架かる橋は、筑前と豊前の境だから両国であるように、
名づけられたときには必ず何らかの意図があったはずなんです。
私の苗字は、「干拓地」を現しています。
私が現在住んでいる「原」は稲作に適さない湿地帯だそうです。
耕作地として期待できるところは「野」です。
そういわれれば確かに、私が高校生になって新しい下水溝ができるまで、
私の家のまわりはよく冠水してました。
それを見越して、私の家も含めて5軒並んだ建売りは、
みな土盛りの上に建っています。
なんかたまには、そういうことを意識した考察もいいかなぁと、
気分が乗ったときは記事にしていきたいと思います。
でも普段はとりあえず、現状を記録する一次資料になればと、
写真中心で行く予定です。これからもよろしくお願いします。
長文失礼しました。