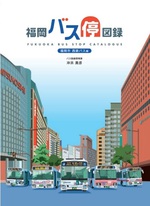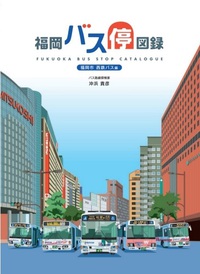2011年05月29日
百木

長崎線の途中、複乗区間の終点「百木」。「ももき」です。

寺川内で古石と分岐する長崎線のバス路線は、そのまま谷筋を進めば、
途中分岐の中小場から進むべきはこちら、百木のほうです。
逆に長崎は、そのまま川を下れば、寺川内ではなく田川のほうに繋がります。
それが、どういう力関係があったのか、人の流れがそうだったのか、
丘を越えて長崎に行く路線が先にでき、百木には当初寄らなかったそうなので、
バスをこちらの集落まで持ってくるのが悲願だった人もいたのかもしれません。


こういう山間部のバス路線では、三叉路で切り返して転回するのが基本なのに、
ここは方向転換のための大きなスペースが設けられています。
この場所も、バスを集落の奥まで通してくれるなら、
と篤志家が無償提供したのだそうです。

そんな想いが込められた碑が、転回場の上に建てられていました。
平成8年路線開設、つい最近のことのようにも感じますが、いちおう15年は経っています。
ただ、バスが移動手段の中心だったのは、昭和50年代まででしょうから、
開設時点からすでに交通弱者のための路線だったのではないかと思います。
そんな産交バスの路線も今月限りです。
代替として、町がバスを走らせるようですけれど。
Posted by ちょんびん at 17:17
│産交バス
この記事へのコメント
こんにちわ!
記念碑建立から15年でしたか。私は計算違いで12年などと偉そうに書いております♪
それにしても折返用地まで無償提供とは、凄い話ですね! 停留所設置に民家の軒先を提供する大分県の例と同じく、バス運行に対する強い協力姿勢を感じます。 ただ、肝心な利用実態がそれくらい強ければよかったんですが…。
記念碑建立から15年でしたか。私は計算違いで12年などと偉そうに書いております♪
それにしても折返用地まで無償提供とは、凄い話ですね! 停留所設置に民家の軒先を提供する大分県の例と同じく、バス運行に対する強い協力姿勢を感じます。 ただ、肝心な利用実態がそれくらい強ければよかったんですが…。
Posted by ハンズマン at 2011年05月29日 22:20
こんにちは。
平成8年と1998年を勘違いされましたかね。
ちょうどバス停を撮っているときに、近所の方がおられて、
その人の甥にあたる人が、折返し用地を寄贈されたそうで、
いろいろとお話を伺いました。
でも、その方も、バスは乗ったことがないらしく、
開設当初から閑散としてたそうなので、
前途多難のなか、よく15年もったということかもしれません。
平成8年と1998年を勘違いされましたかね。
ちょうどバス停を撮っているときに、近所の方がおられて、
その人の甥にあたる人が、折返し用地を寄贈されたそうで、
いろいろとお話を伺いました。
でも、その方も、バスは乗ったことがないらしく、
開設当初から閑散としてたそうなので、
前途多難のなか、よく15年もったということかもしれません。
Posted by ちょんびん at 2011年05月30日 15:45