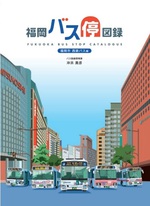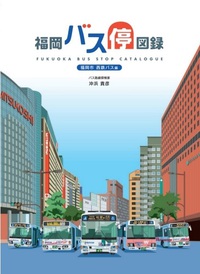2018年09月09日
水迫

はじめて草部南部線に乗ったときから、ずっと撮りたかった風景。
当時の舗装はコンクリートで、
「そのまま農家の倉庫かなんかに突っ込んで終わりそうな道です。」
と表現させていただきました。
■当該記事
http://nishitetsu.yoka-yoka.jp/e507255.html

ではなぜ撮らなかったかというと、すぐ手前に橋があるんです。
草部南部線のハイライトといえる狭い味のある橋が。

だもんで、その橋でバスが走り去るのを待つと、こちら側でバスを待つのは不可能なのです。

バス停の向こうが、田園風景。

水迫。

3便。

菅山側からやって来て、取首を経由して国道325号へ、そして高森方面へ戻るのが草部南部線です。
■草部南部線
http://nishitetsu.yoka-yoka.jp/e1926614.html
続きを読む
2018年09月08日
水湛

阿蘇の外輪山なんですけど、ここは高原というよりは、深い谷なんですよね。草部南部線。

そして雨上がりの橋。蒸せるような空気管が伝わりますでしょうか。

バス停は分岐点。

水湛(みずたまり)。
うちのパソコンでは変換できないので、都度「たたえる」と打って湛の字を出しています。

3便。

交差点には一軒家。

愛想のよいワンコ。

バスが進むほう。

来るほう。
水湛の集落は、バスが走らないほうにあるようですが、行ったことがありません。
バスが走らないので。
続きを読む
2018年09月07日
芹口2018

銀杏が茂り、夏草が伸びて、さらに狭い雰囲気。

まあ実際に狭いわけです。リエッセ限界。

ガードレールの有無がヒヤヒヤ感を大きく左右するということは、
やはりガードレールの設置は安全運行に有用だってことですよね。

芹口で折り返して、戻り。

そして走り去ったら、撮影のため当方はダッシュで車に戻り、このバスを追いかけます。
なんたって1日3便しかないですからね。2時間あまりの1周行程を、
何か所で捕捉できるかによって撮れ高が大きく動くんですよ。

だからこういうバス停周囲写真は、だいたいバスが来る前に撮っているか、
もしくはバスを追いかけ終わってから、再訪して撮っているかいずれか。
どちらにせよ、けっこう非効率なことをやっています。

芹口。ちゃんとバス停も新しく。
■芹口2010 うわもう8年も前なのか!
http://nishitetsu.yoka-yoka.jp/e507237.html

路線によっては3便目がなくなったり予約制のタクシーになったりしてますが、ここは3便健在。

待合のようであって、待合でないようなもの。

木陰で乗客のおばちゃん待機。

大樹。どれくらいの歴史を、ここで眺めてきたのかなぁ。
続きを読む
2018年09月06日
阿蘇山上

ロープウェーの往復記念乗車券を買いまして、えーっと1200円でしたっけ。

でも駅は地震と噴火でこんな感じなので、

バスで来てます。

雄大な阿蘇に、すでに放置された感があるロープのない塔。

もうこのままバスでいいのですかね。

バス待機。

くまもんは車内にもいます。

ぜんそくの方は、火山見学禁止。

灰。

火口。

硫黄。

水面、って呼んでいいんでしょうか、沸き立つもの。

碧玉のような、日常生活で目にしない色です。

避難用のシェルター。

手作り感のあふれる乗り場案内。

車内の熊。最前列の席には、ぬいぐるみがひと席を独占してます。
続きを読む
2017年06月28日
高森町民バス尾下線記事行方不明

根子岳を仰ぎながらゴルフ場の横を走る高森町民バス尾下線。
ツイッターにも投稿したこの画像、ブログにも掲載したはずなのですが、検索しても見つけられません。

冬枯れの中を走るバス。秘境路線バスをゆく3にも掲載いただいた写真です。

牧戸~馬渡間の橋。同じ高森町民バスの草部南部線、水湛~水迫の橋にも劣らない隘路です。
てなことをキャプション付けて、雑誌の発売以降に掲載したつもりなんですが、
下書きの中にも掲載一覧の中にも見つけられないのです。キツネにつままれた気分。
産交バスや高森町民バスで検索してみてもヒットせず、原因不明です。
当ブログ内のどこかで見つけたら教えてください。
続きを読む
2017年06月14日
下山 行き止まり感の最高峰

阿蘇の外輪山、奥に見える盆地は、久住から竹田の付近。

バス通りぽくない細道。

下山バス停。

産交観光。

3便あった尾下線、夕方の便は予約制の乗合タクシーに。
殆どの人が、朝から街に出て、昼便で帰ってくるということですよね。

左に寄せてギリギリを突っ込んで、

回って、

戻ります。乗って体感しましょう。感動します。
続きを読む
2016年08月05日
2016年08月05日
2016年08月04日
味鳥

地図左の黒岩から下の大戸口の方へ抜ける道が整備されていて、
ここ味鳥への道は、まるで山林に入り込む側道のようなところを曲がる必要があります。
そのせいか、道路地図のバス路線も、味鳥には対応できていません。

でも当然ながらバス停は立ってますよ。

味鳥。新仕様。高森町民バス、河原線。

高森町民バス、以前は各系統とも3便ずつの平等主義でしたが、
利用者数や率に大きな違いがあるのか、3便あるものと2便のものができました。
河原線、夕方は予約制の乗合タクシー。
循環線1周してほしいんですけど、という要望は応えてもらえませんよね、きっと。

バス停は公民館の横、突きあたりにあるのが略式の地図。
バスは奥から手前の方へ、一方向の循環です。

前回も掲載した石碑が倒れているのは、経年のせいか、それとも震災の被害なのか。

バスは今日も、元気に走っているはずです。週2回月木だけですが。
続きを読む
2016年08月03日
黒岩

京都市と福岡市の、そこそこ都心部にしか住んだことのない私、
こういうところに道を作ろうと思った人、ここに初めて足を踏み入れた人、
まったく共感できないのですが、尊敬しています。
そういう開拓者精神が、現在の郊外バス路線を生んでいるわけですからw

規定上フリーバスになっているかどうかはともかくとして、
山村部のバスは殆どが、運転士と乗客も顔見知りですし、家の前で停まりますし、
バス停ってのは申請上の記号でしかないのだろう、と感じることしばしば。
集落が散在している場合に、ひとつひとつにバス停を設置するのではなくて、
その間あたりにバス停を目安として置いておき、
あとは家の前で待つ、というような運用が当然のように行われています。
※黒岩がそうだ、というわけではありません。

そして、バス停の周りには何もないのでした。

産交観光時代のバス停が残っています。
九州産交が不採算の田舎路線を整理しようとしたとき、
地元の補助金によって存続されるバスは、完全子会社である産交観光が受託する、
という運用形式にしたのです。この時点で法令上は、走ってるのは乗合ではなく、
自治体が借り上げて走らせてる貸切バス、という名目だったのですね。

ほらね、ホントにバス停の周囲、何もないでしょ。
大分県竹田市荻町まで200メートルくらい。県境の集落です。
続きを読む