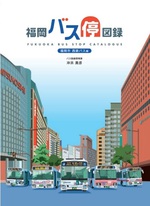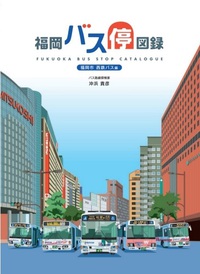2009年01月22日
上田代

上田代。黒木町でも南の端にあります。ひと山越えるとすぐに熊本県です。
このあとに国道3号沿いの「山中」へ行くのも、鹿北廻りのほうが楽です。

店もなく、折返場らしき空間もなく、民家の倉庫の脇に終着点があります。


それでも、2人の乗客がバスで帰ってきました。
いつまでも愛される路線でありますように。 続きを読む
2009年01月21日
日向神


日向神。矢部村の入口に位置する集落です。
以前はここで折り返す設定のバスがありました。
旅館があったり、タクシーの基地があったりして、
観光地として栄えた時期の存在が伺えます。



日向神ダムの向こう側、橋が架かっている先が日向神峡です。
けほぎ岩などの奇岩があり、「けほぎ」は地元の和菓子の名前にもなっています。
けほぎは「蹴洞」と書き、岩山が蹴って穴があいたような形状をしているところから、
この名前がついたようです。
ゆっくりと1泊するにはいい環境ですが、風景以外の観光地があるわけではないので、
大勢の観光客がやってきて賑わう可能性はまずないでしょう。
でも何も見ずに通り過ぎてしまうのはもったいない地域です。

柴庵行のバスがやってきました。バスも風景に溶け込んでいます。 続きを読む
2009年01月13日
柴庵 宮ノ尾



柴庵。矢部村の終着点です。矢部村の役場前からもさほど遠くなく、
傍の商店も開いていて、歩行者もあります。
集落ならば当たり前なのかもしれませんが、堀川バスのほかの終着点では、
なかなか人に出会うことも稀なことを考えれば、さすが本線の終点ですw



矢部村の終着点は、柴庵のほかに宮ノ尾がありましたが、
現在は柴庵に統合されています。
星野村の十篭と板屋くらい離れていると、途中に折返し点を設ける意味がありますが、
矢部村のほうが中心部に集落がまとまっている感じです。
収入を得る術があるのならば、こういうところで暮らしてみたいです。 続きを読む
2009年01月13日
グリーンピア八女

グリーンピア八女。「年金保養施設」ってやつです。
昔の路線図を見ると、バス停名がそのものずばり「年金保養施設」だった時があるようです。
ここまでの路線バスが生き延びているのが不思議。


まあこんな山奥にこんな立派なものをよく作ったねぇ、
作ったらこんな山奥でもたくさんの人が来てくれるとホントに信じてたのかねぇ、と
伺ってみたいものであります。でも息子と来たら楽しそうです。


ただただ広い敷地の一角に、バスが一台ぽつんと停まっています。
2009年01月13日
大藤前

大藤前。宗真寺下→鹿子尾方面のバス停。
矢部線が廃止されて、黒木町から鉄道が姿を消して久しいですが、
バス停の表示にはまだ名残があります。
黒木駅前バス停は、現在「上町」という淡白な名称になっています。

宗真寺下方面は枝線なので、黒木駅前の表示も放置なのかなと思いきや、
本線のバス停もそのままでした。
鉄道の記憶が消えないよう、敢えて残している可能性もありますね。


黒木から上陽(北河内)への中原トンネル跡。大藤前からは徒歩20分くらい。
現在は焼酎保存用の蔵として使われていることでも有名です。
入口に「古久蔵」の木板が掲げられています。


大藤の下を通過するグリーンピア行きです。
2009年01月13日
宗真寺下


宗真寺下。丘の上には黒木保育園があります。保育園の門の先に寺がありますので、
保育園は宗真寺の経営なのでしょう。



折返場は広々と立派です。上田代行のバスは、ここを始発として出発し、
黒木町の中心部を通り抜けて、中篭から南へ向かっていきます。
黒木の発着所が黒木町の入口にあるので、町内の足を補完する意味もあるのでしょう。

宗真寺下折返場の奥には黒木中学校があり、
この折返場の「駐車禁止」の看板もなぜか黒木中学校長名義です。
上田代方面から黒木中学への通学バスの性格もあるのかもしれません。
残念ながら、私は会社勤めのサラリーマンなので、
通常のバス停訪問は土日祝日にしか行うことができません。
平日の生活路線としてどのような利用のされ方をされているのか、
生で触れる機会があると、その路線の印象もまた違ったものになるでしょう。
2009年01月13日
鹿子尾


鹿子尾。山あいのバス路線の終着点には、必ず川の流れがあります。
山を川が削って幾許かの平地をつくり、そこに人の生活が営まれるからでしょう。
そしてバス停の袂には、小さな商店があることが多いです。
また集落の目立つ場所には、現在の人口からすると立派過ぎるくらいの規模の、
神社仏閣が設けられていて、田舎暮らしと信仰の関係を垣間見ることができます。


黒木からのバスは道幅をいっぱいに使って鹿子尾にやってきて、
橋を渡って向こう岸の駐車場でとまるかな、と思ったら、そのまま奥へ走り去りました。


あれれ?と思って追いかけると、かなり先にもうひとつ集落がありました。
上鹿子尾。こちらにバス停はありませんが、待機場が設けられています。
乗りたいと意思表示をすれば、ここからでも乗せてくれることは間違いないです。
堀川バスの終着点は、板屋や桐葉のように、これより上にはもう民家ないよ、
という場所に設けられているのですが、ここだけなぜバス停がないのか不思議です。

このへんが八女茶の発祥の地らしいです。