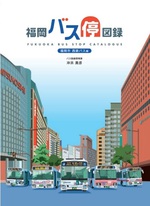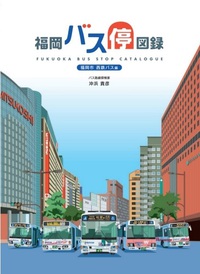2009年01月27日
道崎


道崎はまっすぐに伸びる道路の途中の終着点。
といっても終着なのは佐賀市営バスだけで、西鉄が寄人橋を経由して久留米まで行きます。


久留米方面行バス停、すなわち終着バス停と折返場がかなり離れており、
折返場の脇に佐賀方面バス停があります。
「どっちで降ります」と運転手さんに聞かれましたので、目的地に近いほうを選べるようです。

折返場は市営住宅の一部敷地を借用したような形式です。
この先はすぐ旧千代田町ですので、佐賀市の端っこまできているのですが、
諸富や鍋島に比べると佐賀中心部から近いので、郊外という感覚はありません。
道崎行は、「57」社会保険病院経由と「28」東佐賀経由の2系統があり、
「57」で道崎に来たバスは「28」で折り返し、「28」は「57」で折り返すダイヤなので、
2系統の乗車体験をするには効率のいい路線です。
「28」は「エスプラッツ」を経由する唯一の系統でもあります。
2009年01月27日
佐賀市営バス 行先番号のつけかた

佐賀市営バスは、すべてのバスが佐賀駅バスセンターを経由します。
そして、始発地がどこであっても、佐賀駅バスセンター行は「1」なのです。
「2」は、佐嘉神社行。
ちゅーことで、2つの系統が通るバス停の場合、
市内方向へ行くバスは行先番号で経由地の判断ができません。
たとえば「咾分」で「1 佐賀駅バスセンター」行が来た場合、
それが「23」の折返しであれば南里経由ですが、「25」であれば広江経由です。
これが不便だという声があがってこないということは、
殆どの需要が郊外と市内中心部(駅~県庁前・片田江あたり)の相互往復のみであって、
たとえば立野と犬井道のような、郊外バス停相互間の利用は想定されないということでしょう。

これは橋津の折返場に停車中の、蓮池経由の「1」佐賀駅バスセンター行です。
でも経由地は「県庁前 唐人町」なので、諸富経由と見分けがつきません。
確かに、佐賀市営バスの路線は、終着点からすこし伸びればほかの系統に届くのに、
そこまで行かない終着点というのが多数あります。
「早津江~和崎」「久保泉団地」「千布」「運転免許センター~川久保」などです。
以前は路線があったのに短縮されて現在の姿になったものも多く、
市内中心部以外の相互輸送は採算が合わないということは、
実際の運用の中で検証された事実なのかもしれません。
ならば、全ての中心部向けが、行先ごとに同じ番号なのは、とても合理的なのでしょう。
徳永から清友病院なんて需要があれば、久保泉団地が終点にならず、
川久保までの路線が走り続けてるはずですもんね。
西鉄バスでも「四箇田団地~福大病院」「桧原営業所~那珂川営業所」というような、
均一区間を通らない横連携路線が成功していないですから、
都心に向かわない需要を安定して喚起するのは、とても難しいことなのでしょう。
でも全ての天神行が「1」になったら混乱するだろうなぁw
西鉄バス圏内に30年暮らしていますので、行きと帰りは同じ番号なのが当然という感覚があり、
その「当然」を覆されるのはとても新鮮です。
タグ :佐賀市営
2009年01月26日
大詫間


大詫間。大きな集落です。人口も数千人規模でいると思います。
和崎から川副大橋を渡って大詫間へアクセスしますが、
大詫間側は民家が密集しているのが見えて、繁栄していた時期があることを感じます。
わたしは不勉強なのでどんな産業があるのか知りませんが、やはり海苔でしょうか。
バスの終着点は、「ただそこに折返場をつくるスペースがあったから」設けられていることも多いです。
田舎の集落端まで走っているバスの場合は、終着点はいい雰囲気なのですが、
まわりに数十軒の家があるだけで、それ以外どこにも行きようがないことがほとんど。
けれども大詫間は、もう一度訪れて何時間か散歩してみたい「奥行き」が感じられました。私好みです。


バス停自体は生活道路の途中にあって、終着点という雰囲気は薄いです。
商店や農協があって、人が集まる場所なのでしょうが。


折返場は小学校の校庭裏のような場所で、L字型になっています。
大詫間まで南向きに走ってきたバスは、Uターンするように北向きに折返場に突っ込み、
東側に向かって90度カーブしながらバックします。土地有効活用です。
写真を撮っていたら、待機中の運転手さんに「撮りましょうか?」と声をかけていただきました。
ありがとうございます。バス好きもこうやって認知されるくらいは居るんでしょうね。
わたしはバスとその周囲の風景があれば、自分が一緒に写りたいとはまったく思いませんが。 続きを読む
2009年01月26日
和崎

佐賀駅バスセンターから、こんどは「25」で和崎へ向かいます。
「袋」までは空港へのアクセス道路を通るので広い道なのですが、
そこから広江までは旧道を縫うように南下して行きます。乗りごたえあり。


和崎の折返場。集落は南側に広がっています。
和崎では「23」の大詫間線に接続しています。
先の交差点を北に向かえば、早津江へもそう遠くはありませんが、今は路線がありません。
あくまで中心部と郊外を放射状に結ぶのが主眼であり、
横連携の路線では採算が合わないという判断なのでしょう。


この道路は国道444号線ですが、折返場がある北側には、なーんにもありません。
そして、佐賀はほんとに平野だなぁ、と実感できます。坂もないです。
続きを読む
2009年01月25日
博多ふ頭から博多方面へ

博多ふ頭にて「46」を撮影しました。日中は1時間に2本ダイヤです。
「天神 キャナルシティ 博多駅 井尻四角」行と表示されています。
博多ふ頭からの需要は、天神・キャナルシティ・博多駅が主要なところでしょう。
けれども、博多駅に行きたい人は、「46」には乗らないほうがいいです。
天神から国体道路、キャナルシティを経由しますので、
国際センターから大博通りをまっすぐ下る「47」「48」に比べると、所要時間がかなり長いです。
にも関わらず、大書されている行先は「博多駅」。
ここで強調すべきは、「天神」か、「46」が唯一アクセスする「キャナルシティ」でしょう。

「48」の表示は、当然「博多駅」が強調されます。
「46」はこれと差別化をおこなっておかないと、利用者が確実に混乱します。
それと、博多ふ頭からキャナルシティへのアクセスが「46」だけというのも、本数、経路共に不便です。
併せて、中央ふ頭発の「80」も、天神を経由しないとキャナルシティへ行けないのは、
直行したい客にとってはとても無駄な時間がかかるように思います。
博多ふ頭はともかく、中央ふ頭からの乗客は韓国からの観光客がかなり多いでしょうから、
海外観光客の人気スポットであるキャナルシティは、もっと優遇されてよいのでは?
ということで、博多ふ頭や中央ふ頭から博多までのバスは、築港本町か蔵本交差点から東に向かい、
土居通り→櫛田神社前→キャナルシティという
「ぐりーん逆回り」ルートを辿ってもらいたいと思うのですが、いかがでしょうか。
個人的に、土居通りに路線バスが走ってるのを見たいだけと言われれば、反論できませんが。
2009年01月25日
雪の福岡

この週末、福岡は雪で都市高速が通行止めです。(写真は築港ランプ)
都市高速経由の路線パスは、一般道に迂回してきます。
那の津通りの長浜ラーメンの前、しかも追い越し車線の方を、「204」や「305」が走ってたりして、
すれ違うと「おおっ!」と嬉しくなります。


大博通り、築港本町の交差点を那の津方向へ左折する「39」。
呉服町ランプから西公園ランプまで都市高速を経由する路線の迂回です。
一般の方は、ここでバスにすれ違っても、何が特別なのかも気づかない方がほとんどでしょうが。
よい日でした。 続きを読む
2009年01月24日
山中


山中。もとは西鉄バスが走っていましたので、バス停も西鉄バス仕様のものを、
上から「堀川バス」のシールを貼って使用しています。
堀川バスのスタンダードデザインとは違うのが、バス好きにはたまりませんなw

南側は「小栗峠」という峠まで1キロ足らずです。
西鉄バスが山鹿まで直通していた頃は、「小栗峠口」というバス停があり、
それを越えると熊本県です。
いまは福岡側を「山中」まで堀川バスが担当し、
熊本県側は道の駅から山鹿までを九州産交バスが担当しています。
路線は分断されましたが、1時間くらいあれば歩ける距離です。



八女方向は、福島発着所行。

ということで、この路線は福島~山中間を走っているわけなのですが、
バスの表示は「八女~辺春」。エリア表示のほうがわかりやすいという判断でしょうが、
「山中行きに、終点の山中まで乗って」という指示を受けた場合、まずこのバスには乗れませんね。

通学時間帯にバスがないので、スクールバスか何か、送迎があるのでしょう。
バス停が集合場所として使われています。なんか本末転倒ぽいです。
ということで、堀川バスの終着点めぐりも、
残すところは医療センター(鑓水)とJR久留米だけとなりました。 続きを読む